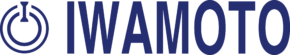猛暑や巨大な台風、これまでになかった規模の山火事。地球温暖化の影響による異常気象や自然災害は、年々発生の頻度が増えています。実際に、気温の上昇や天候の変化による不作、農作物の成長を阻害する害虫の出現などが観測され食の供給システムの持続可能性が問われています。このような食に関する課題を解決する可能性を持つアイデアが世界中で生まれています。陸上植物を水中で生産する世界初のプロジェクト水中菜園「Nemo’s Garden」は、大きな風船のような6つの透明なプラスチックのドームで構成されている。それぞれのドームは水面下約15〜36フィート(約4.5m〜10m)の深さに浮かんでおり、ロープやネジで海底に固定されている。ひとつのドーム内には90以上の苗床が備えられ、レタスやバジルといった植物や野菜を栽培することができる。この水耕栽培では、植物の根に栄養素や水分を供給する肥沃な土壌を必要としないことが特徴。干ばつや砂漠化などにより陸上での農業が難しくなっても、将来的には海の中で植物を生産することが可能になるかも知れず、さらに水中菜園のプロジェクトは、長期的な視点で環境に悪影響を与えない農業の形態を目指しているため、太陽の光と、海水淡水化による新鮮な水から生み出された再生可能なエネルギーをシステムを動かすために使用している。24時間365日監視され、細かいデータの計測が行われているため、最適に管理された環境下で植物を生産することができる。今まさに行われている世界で初めての水中菜園の実験。もちろん、地球温暖化による気温上昇や気候変動は最小限に抑えるように取り組みを行なっていかなければならない。しかし、食の生産方法が多様化することは、イタリアだけでなく、世界のあらゆる所で貧困や飢餓に苦しむ人々の救いになる可能性も有ります。
私は常日頃地球の飢餓や貧困は人間の叡智で必ずや克服できると信じています。我が日本でも 海藻産業・食文化・地域社会・海の生態系の間に、よい循環が生まれる社会の仕組みづくりも目指している 合同会社シーベジタブル 代表を務める蜂谷潤(はちや じゅん)氏と友廣裕一(ともひろ ゆういち)氏の二人が挑戦するのは、絶滅の危機にある海藻の再生と新たな「海藻食文化」の創造。 「1980年頃には全国に20万ヘクタールあった藻場が、現在は10万ヘクタールくらいまで減っていますが、これは単に、海藻が食べられなくなってしまう、という人間にとっての問題だけではありません。
藻場はいわば、海の森。水生生物の産卵・繁殖の場所として海の多様性を支え、また海中への酸素供給を担っています。そのため、海藻の減少が地球環境に与える影響も少なくなく、大学在学時から海藻に興味を抱き、画期的な海藻栽培の技術を発明した蜂谷さん。現在ではシーベジタブルとして全国各地に拠点を持ち、海藻の陸上栽培・海面栽培をおこなっています。いま、日本の海藻に何が起こっているのか。そして、シーベジタブルは海藻の栽培を通じて、どんな未来を創出しようとしているのか。蜂谷氏は「藻場は魚の隠れ場所になるだけでなく、生物ピラミッドの底辺となる海藻植物プランクトンの産まれる場所でもあります。数ミリ単位のヨコエビやワレカラといった小さな生き物がいて、それを食べる小魚がいて、大きい魚がいて・・・、藻場がなくなればプランクトンや小魚が減ることで海中の栄養分も減少し、そこに支えられている生物多様性も消えてしまうのです。そんな背景を飛ばして、『大型魚がいなくなったぞ!マグロが減っている!』みたいな報道ばかりがされています。」海藻産業・食文化・地域社会・海の生態系の間に、良い循環が生まれる社会の仕組みづくりも目指しています。
身近な現象でも富山の白エビやホタルイカ、石川県のスルメイカなどが9割減、サンゴ礁と極端な減少は温暖化の影響や地殻変動などでしょうが廃プラや生活(特に規制の緩い発展途上国の)工業廃水などなども。
米騒動は明らかに人そのものの政策に起因しますが、高邁な志しを抱いている若者達には善の循環を触発し果敢に諸問題を解決して頂けると信じて居ます。